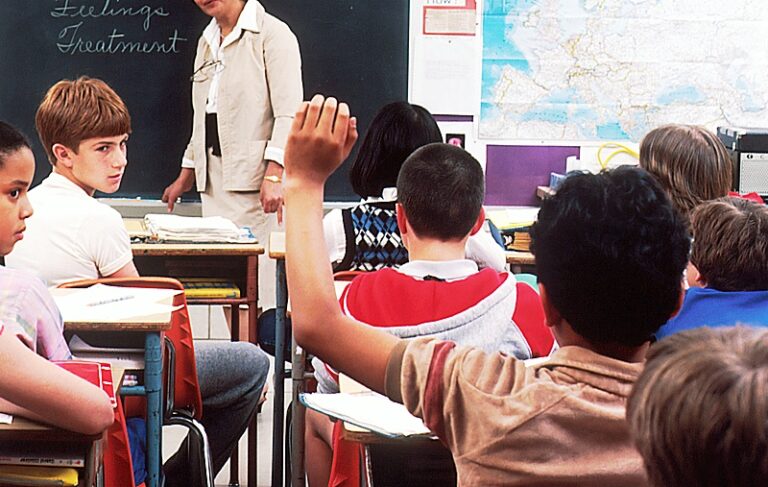教員免許を持っている人の割合がどのくらいなのか、気になったことはありませんか?また、教員免許取得率と大学ごとの違いについても興味を持っている方は多いでしょう。
教員免許授与件数の推移や、教員免許を持ってるだけでどのようなメリットがあるのか、本記事では詳しく解説していきます。
さらに、教員免許を持ってるだけだと教師になれるのか、教員免許を活かした副業にはどんなものがあるのかも紹介します。教員免許の取り方と難易度についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。
【この記事で分かること】
- 教員免許を持っている人の割合
- 教員免許取得者が教育業界で働いていないケース
- 大学ごとの教員免許取得率の違い
- 教員免許を持っているだけのメリットとデメリット
教員免許を持ってるだけの割合はどのくらい?

- 教員免許を持っている人の割合は?
- 教員免許取得率と大学ごとの違い
- 教員免許授与件数の推移とは
- 教員免許を持ってるだけのメリットとは?
教員免許を持っている人の割合は?
教員免許を持っている人の割合は、文部科学省が公表する「教員免許授与件数」や「教員免許保有者数」から知ることができます。近年では、大学や教育機関で教員免許を取得する人が一定数いる一方で、実際に教職に就く人の割合は減少傾向にあります。
例えば、教員免許を取得したものの、別の職種に進む人や、免許を活用せずに一般企業に就職するケースも少なくありません。そのため、教員免許を持っている人の全体数と、実際に教師として働いている人の割合には大きな差があります。
また、ペーパーティーチャー(教員免許を取得しているが教職に就いていない人)の存在も増えており、教育業界以外でも活用できる資格として教員免許を取得する人もいます。このように、教員免許を持っている人の割合は一定数存在するものの、必ずしも教職に就くとは限らないのが現状です。
教員免許取得率と大学ごとの違い

教員免許の取得率は、大学や学部によって大きく異なります。特に、教育学部や教職課程が充実している大学では、多くの学生が教員免許を取得します。一方で、一般的な文系・理系学部では、教職課程を履修する学生の割合は低くなります。
例えば、国立大学の教育学部では、ほぼ全員が教員免許を取得することが一般的です。対して、私立大学の一般学部では、教員免許を取得する学生の割合は限られており、大学によって取得率に大きな開きがあります。
また、大学によっては教員採用試験のサポート体制が異なるため、取得率だけでなく、実際に教員として働く割合にも差が生じます。教育に特化した大学では、教員免許の取得が前提となることが多いため、取得率が高くなりますが、一般的な大学では「取得はしたが、教職には進まない」というケースも珍しくありません。
このように、大学ごとに教員免許取得率に違いがある背景には、カリキュラムや学生の進路志向、サポート体制など、さまざまな要因が影響しています。
教員免許授与件数の推移とは?
教員免許の授与件数は、毎年文部科学省から公表されており、時代の変化とともに増減を繰り返しています。近年では、少子化の影響や教員の労働環境の問題も相まって、取得者数が減少傾向にあるとされています。
例えば、1990年代から2000年代初頭にかけては、教員免許の取得者数が比較的多い時期でした。この背景には、安定した職業としての教員の人気や、大学側の教職課程充実が挙げられます。しかし、その後は民間企業への就職を希望する学生が増えたことや、教育現場の厳しさが広く知られるようになったことなどが影響し、授与件数は減少傾向にあります。
一方で、特定の分野では教員不足が問題視されており、理数系や特別支援教育の分野では、教員免許を持つ人材の確保が重要視されています。このため、近年では教育政策の見直しにより、特定の免許取得を後押しする動きも見られます。
今後の推移については、社会全体の教育ニーズや労働環境の改善状況によって左右されるでしょう。特に、働きやすい環境が整えば、教職を目指す人が増え、授与件数が再び増加する可能性もあります。
教員免許を持ってるだけのメリットとは?

教員免許を持っているものの、教師として働いていない人も多くいます。しかし、教員免許を「持ってるだけ」でも、いくつかのメリットがあります。
まず、教育関連の副業や講師業に活かせる点です。例えば、学習塾や家庭教師、企業研修の講師など、教育経験を求められる仕事では、教員免許を持っていることが有利に働くことがあります。また、学校以外の教育機関でも、教員免許を持っている人が優遇されるケースもあります。
次に、履歴書や資格欄でアピールできる点です。たとえ別の業界に進んでも、「計画的に学び、国家資格を取得した」という事実は評価されることがあります。特に、公務員試験や教育関連の企業では、一定の信用につながることもあります。
ただし、デメリットとしては、実務経験がないと免許の価値が十分に活かせない点が挙げられます。教員免許を持っていても、実際に教壇に立った経験がないと、教育業界での転職には不利になる可能性があります。そのため、資格を持っているだけで満足せず、必要に応じて教育現場での経験を積むことが重要です。
このように、教員免許を持っているだけでも一定のメリットはありますが、より効果的に活用するためには、実務経験を積んだり、関連分野での仕事に挑戦したりすることが大切です。
教員免許を持ってるだけの割合と活かし方

- 教員免許を持ってるだけだと教師になれる?
- 教員免許を活かした副業には何がある?
- 教員免許がなくてもできる仕事とは?
- 教員免許を取ればよかったと後悔するケース
- 教員免許の取り方と難易度
- 高校生が教員免許を取るには?
- 大学生が教員免許を取る方法
- 社会人が教員免許を取る方法
- 教員免許を持っているだけの割合に関する総括
教員免許を持ってるだけだと教師になれる?
教員免許を持っているだけでは、すぐに教師として働けるわけではありません。公立学校の教員になるには、教員採用試験に合格する必要があり、免許を取得しただけでは自動的に教師として採用されるわけではないのです。
一方で、私立学校や非常勤講師の募集では、教員免許を持っていれば応募できるケースもあります。ただし、採用の際には指導経験や専門知識が求められるため、教育実習やボランティア活動などの経験があると有利になります。
また、教育委員会や学校現場では、臨時的任用教員(臨時講師)の枠を設けていることがあり、正式な採用試験を受けなくても、短期間の契約で教師として働ける可能性もあります。しかし、安定した雇用を目指す場合は、やはり採用試験の合格が不可欠です。
このように、教員免許を持っているだけでは教師にはなれませんが、非常勤講師や臨時採用などの道もあるため、自分のキャリアプランに合わせた選択が重要です。
教員免許を活かした副業には何がある?
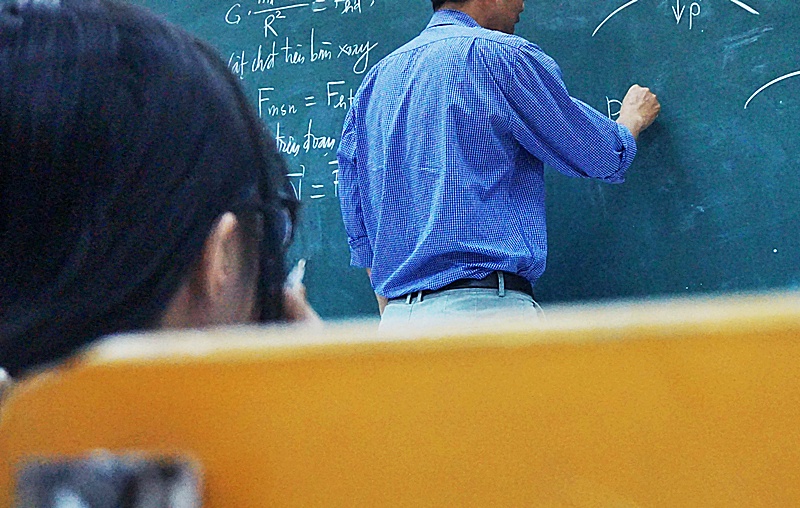
教員免許を活かせる副業には、教育に関わるさまざまな仕事があります。代表的なものとして、家庭教師や塾講師が挙げられます。特に、教員免許を持っていることで保護者からの信頼を得やすく、高時給の案件に採用されることもあります。
また、オンライン講師としての活動も増えており、学習支援プラットフォームや動画配信サイトを活用して授業を提供する人もいます。特定の科目に強みがある場合は、受験対策講座や専門講座を開くことで、安定した収入を得ることが可能です。
さらに、企業向けの研修講師や教育コンサルタントとしての仕事も選択肢の一つです。社会人向けの研修では、プレゼンテーション力や指導スキルが求められるため、教員経験があると有利に働くことがあります。
ただし、副業をする際には、勤務先の規則を確認することが重要です。特に、公立学校の教員は副業が制限されることが多いため、事前に許可を取る必要があります。
このように、教員免許を活かした副業は多岐にわたります。自分の得意分野や働き方に合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。
教員免許がなくてもできる仕事とは?
教員免許がなくても、教育や指導に関わる仕事は数多くあります。例えば、学習塾や予備校の講師は、教員免許が不要な場合がほとんどです。特に実績や専門知識が評価されるため、指導経験がある人や得意な科目がある人に向いています。
また、企業の研修担当者や社員教育に関わる仕事も、教員免許がなくても可能です。人材育成を担当する職種では、教育学の知識よりも実務経験やコミュニケーション能力が重視されます。そのため、教育業界以外から転職する人も多くいます。
さらに、子ども向けの習い事講師やスポーツインストラクターも、教員免許がなくても働ける仕事の一つです。ピアノや英会話、水泳など、専門スキルを活かした指導が求められるため、実技指導に自信がある人には適した職業です。
このように、教員免許がなくても教育に関わる仕事は多数あります。指導スキルや専門知識を活かせる分野を見つけることで、教育業界でのキャリアを築くことも十分可能です。
教員免許を取ればよかったと後悔するケース
教員免許を取ればよかったと後悔するケースは、主に転職やキャリア選択の場面で起こります。例えば、教育関連の仕事に就きたいと思ったときに、教員免許が必要な職種に応募できず、選択肢が限られてしまうことがあります。
また、公務員試験や教員採用試験を受ける際に、すでに社会人になってから「教員免許を持っていれば有利だったのに」と感じる人もいます。特に、学校教員だけでなく、教育行政や研修担当の職種でも、免許があることで採用が有利になるケースがあります。
さらに、子育てをきっかけに教育に興味を持ち、「教員免許を取っておけば、子どもの教育にもっと役立てられたかもしれない」と感じる人もいます。教育の知識や指導経験が、家庭内でも活かせることを実感し、後悔することがあるのです。
とはいえ、社会人になってからでも教員免許を取得する方法はあります。通信制大学や科目履修制度を活用すれば、働きながらでも免許取得を目指すことが可能です。もし後悔を感じているなら、今からでも取得に向けて行動することが一つの選択肢となるでしょう。
教員免許の取り方と難易度
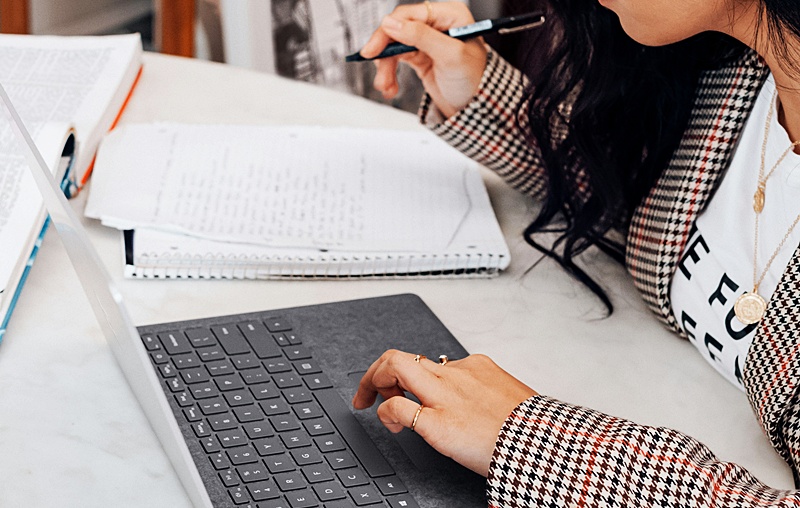
教員免許を取得するには、主に「大学で必要な課程を修了する方法」と「特例制度を活用する方法」の2つがあります。一般的なのは、大学で教職課程を履修し、教育実習などの必須単位を修得して免許を申請するルートです。この方法では、学士号の取得と並行して教員免許を得られるため、多くの人が選択しています。
一方で、すでに大学を卒業している人は、通信制大学や科目履修制度を利用して単位を取得することで、免許取得が可能です。ただし、教育実習を含むため、仕事と両立しながらの取得は一定の負担が伴います。
難易度に関しては、教員免許そのものの取得は、学習意欲があれば十分に可能なレベルです。しかし、取得後に公立学校の教師になるためには、教員採用試験に合格する必要があり、この試験は自治体や教科によって倍率が大きく異なります。特に、小学校教員は比較的倍率が低い傾向にある一方で、中学校・高校の専門科目では倍率が高くなることもあります。
また、大学によって教職課程のカリキュラムや求められる学習量が異なるため、進学前にしっかり確認しておくことが大切です。
高校生が教員免許を取るには?
高校生の段階では、まだ教員免許を取得することはできません。しかし、将来教員を目指す場合、進学先の選び方が重要になります。教員免許を取得するには、文部科学省が認定する「教職課程」がある大学に進学する必要があるため、大学選びの際には事前に確認しておくことが大切です。
また、国公立大学だけでなく、私立大学や短期大学、通信制大学でも教職課程を設けている学校があります。自分の学びたい教科や将来のキャリアプランに合わせて、適した大学を選ぶことが求められます。
高校生のうちにできる準備としては、教育関連のボランティア活動に参加したり、子どもと接する機会を増やしたりすることが挙げられます。例えば、学習支援のボランティアや地域の児童施設での活動を経験すると、教員になった際に役立つスキルを身につけることができます。
また、教員採用試験は自治体ごとに異なるため、将来どの地域で教員を目指すのかを考えておくことも重要です。早い段階から情報を集め、必要な資格や試験対策について理解を深めることで、スムーズに教員免許取得へと進むことができます。
大学生が教員免許を取る方法
大学生が教員免許を取得するには、文部科学省が認定した「教職課程」のある大学に在籍し、必要な単位を修得することが基本です。通常、教育学部や教職課程を設置している学部に所属し、専門科目・教育関連科目・教育実習などを履修することで、卒業時に教員免許を申請できます。
大学での履修内容は、小学校・中学校・高校のどの教員免許を取得するかによって異なります。例えば、小学校教員を目指す場合は幅広い教科の指導法を学ぶ必要がありますが、中学・高校の教員免許を取得する場合は、特定の専門科目を重点的に学ぶことになります。
また、大学の学部によっては、教職課程を履修しないと卒業後に教員免許を取得できない場合があります。そのため、教員を目指す大学生は、早い段階で履修計画を立てることが重要です。特に、教育実習は必修科目であり、一定期間学校での実習が必要なため、スケジュール調整も必要になります。
さらに、一般的な大学とは別に、教員養成を専門とする「教員養成系大学」や「教育大学」に進学すると、より体系的に教員になるための知識やスキルを身につけることができます。大学選びの段階で、どのような進路を考えているのか明確にしておくと良いでしょう。
社会人が教員免許を取る方法
社会人が教員免許を取得する方法はいくつかありますが、主なルートは「通信制大学・大学院を利用する方法」と「科目履修制度を活用する方法」です。すでに大学を卒業している場合、これらの制度を利用することで、働きながら免許取得を目指すことができます。
通信制大学では、教職課程のある学部に入学し、必要な単位を修得すれば教員免許を取得できます。通学の必要がないため、仕事と両立しながら学べる点がメリットです。ただし、教育実習は必修科目のため、一定期間勤務を調整する必要があります。
また、すでに大学で取得した単位を活かせる「科目履修制度」も有効な方法です。この制度では、不足している教職課程の単位だけを履修することができるため、短期間で免許取得が可能になるケースもあります。
さらに、特定の条件を満たせば、社会人向けの「特別免許状制度」や「教職経験者特例制度」を利用できる場合もあります。これは、一定の実務経験がある人を対象に、通常のルートとは異なる形で教員免許を取得できる制度です。特に、企業経験を活かした専門科目の指導を行う場合などに適用されることがあります。
社会人が教員免許を取る際は、学習にかかる時間や費用、実習期間の確保などを事前に確認し、無理なく進められる方法を選ぶことが大切です。
教員免許を持っているだけの割合に関する総括
- 教員免許を取得しても教職に就かない人が一定数いる
- 取得者全体の中で実際に教員になる割合は低下傾向
- 資格を取得するものの異業種へ進むケースが増加
- 教職以外の道を選ぶ理由は待遇や労働環境の影響が大きい
- 一部の取得者は非常勤や臨時採用にとどまる
- 資格を取得後すぐに別業界に進む割合も無視できない
- 民間企業での就職を選択する教員免許取得者が増加
- 大学や教職課程修了後に進路変更するケースが多い
- 教員不足が叫ばれる一方で免許保有者の活用が進んでいない
- 地域や教科によっては教員志望者の不足が深刻
- 教員免許を取得したが教育関連職に就かない人も多い
- 免許を活かせる職業は教職以外にも存在
- 取得後に公務員試験や一般企業の就職活動へ移行する人も多い
- 教員採用試験の倍率や難易度が進路決定に影響
- 免許取得者全体のキャリアパスが多様化している